著者:穂村弘(ほむら・ひろし)
1962年北海道生まれ。歌人。
2008年「短歌の友人」にて第19回伊藤整文学賞<評論部門>受賞。
「マスター、最近ノダちゃん顔見せてる?」
お店に入ってくるなり大声を出すひとがいて、びくっとする。それ、合ってるのかなあ、と訝しい気持ちになる。でも、誰もそうは思ってないようだ。「マスター」も「このところお見かけしませんね」と自然に応えている。じゃあ、これが普通なのか。多分そうなんだろう。だって、そのお客さんには沢山の友だちがいて仕事もばりばりやって家庭も営んで趣味も充実している(その後の数分間で本人が語った言葉より)らしいのだ。
でも、私には無理だ。「マスター」「ノダちゃん」「顔みせてる?」のなかのどれひとつでも、口に出したくはない。ただ、何故そんなに嫌なの、と訊かれるとうまく説明できない。単なる自意識過剰だろうか。そうは思いたくない。世界とか他者とかコミュニケーションに対するズレがまず先にあって、一瞬ごとに痛みを感じるので、結果的に自意識過剰になっている、と思いたい。もともと内気なわけじゃなくて、波長がズレているこの世界では、うまく生きることができなくて心を削られるから萎縮してしまうのだ。
しかし、この結果的な内気さは致命的だ。いや、現実世界のなかでは、内気だけが致命的なんじゃないか。それ以外のどんな弱点や欠点があっても、本人が怯むことなく一定量の活動性を維持できれば、「マスター、ノダちゃん」の彼のようにちゃんと自分の居場所をみつけて機能することができるのだ。
以前、或るトークイベントのとき、会場のお客さんに向かってこんな質問をしたことがある。「このなかで好きなタイプはヤクザという女性は手を挙げてください」
全く手は挙がらない。いなーい、いるわけなーい、という雰囲気で一杯になる。その場に十倍の人数の女性がいても結果は同じだったかも知れない。だが、と私は思う。現実のヤクザには必ず女がいるではないか。大抵は美人で、かつ複数いたりもする。これをどう説明するのか。私にはわかる。ヤクザは内気ではないからだ。
好みのタイプはヤクザというひとが仮に全女性のなかの0.001パーセントだとしても、これに全人口の半分を掛ければ相当な数になる。そして、ヤクザはヤクザであることを常に一貫して外部にアピールし続けている。これが重要なのだ。
同様に「マスター、ノダちゃん」なひとは、いつでもどこでもお店に入ってきた瞬間に「マスター、ノダちゃん」なひとであることがわかる。だから、それを繰り返すうちに必ず波長の合う他者と出会って、自分の居場所をみつけることができる。
一方、店の片隅で「それ、合ってるのかなあ」と心のなかで思っているだけの私がどんな人間なのかは周囲の誰にもわからない。仮に「マスター、ノダちゃん」な彼よりも私の性質の方が多くの他者に好ましいとしても、結果的に内気であるということが、世界との出会いの可能性をゼロにしてしまうのだ。
どんなキャラクターであっても、この世のどこかには居場所がある。電車のなかでみかける説教好きなセクハラ酔っぱらいおじさんも、ちゃんとネクタイを締めて結婚指輪をしているではないか。でも、内気だけは駄目。伝わらない心を抱えていながら、どうすることもできない。時間だけがどんどん過ぎる。だからこそ内気なのだ。
そんな或る日、私は心を決めた。そして様々な原稿のなかで、「私の心は硝子のように壊れやすい」とか「ベッドで菓子パンを食べる」とか主張し始めた。だって、ヤクザはひと目でヤクザってわかるけど、「壊れやすい」とか「ベッドで菓子パン」とかはひと目ではわからない。云われなければ、永遠に誰にも気づかれないままなのだ。新聞や雑誌にそんなこと書きまくってどうかしてるんじゃないの、という声も聞こえてきたが、私は怯まなかった。いや、怯んだが、どうかしたままだった。
その結果、初対面のひとに挨拶すると、「ああ、あの、ベッドで菓子パンを食べる……」と云われるようになった。みんなにこにこしている。やっぱり、と思う。「ベッドで菓子パンを食べる」人間が好きなひとも世界には存在するのだ。
だが、他者の笑顔と引き替えに、私は真の内気さを失った。「私の心は硝子のように壊れやすい」というアピールは、本当に内気な人間にはできない。でも私はやった。これ、合ってるのかなあ。不安だが仕方ない。望み通りになったのだ。
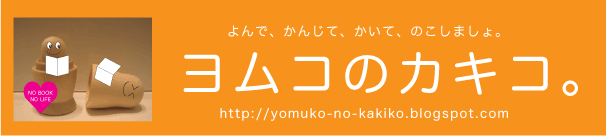

0 件のコメント:
コメントを投稿